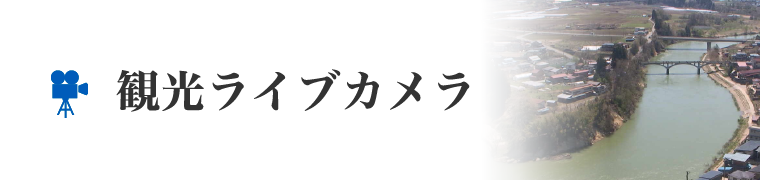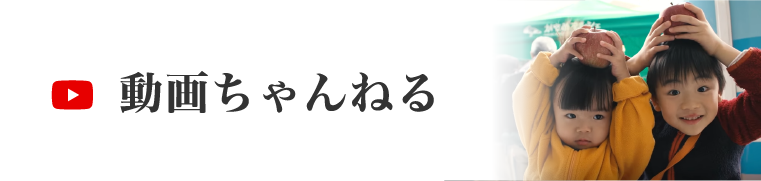国民健康保険税
国民健康保険税とは
保険税は医療機関で支払う一部負担金とともに、国保を支える大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。
保険税を納めるとき
保険税は国保の資格を得た月の分から納めます。また、保険税を納める義務は世帯主にありますので、世帯主が国保に加入していなくても、納税通知書は世帯主に送られます。
保険税の決まり方
以下の組み合わせで世帯ごとの保険税額が決められます。
40歳以上65歳未満の人は(介護保険の第2号被保険者として)医療保険分と後期高齢者支援金分と合わせて介護納付金分も納めます。
令和7年度の国民健康保険税の税率等は次のとおりです。
| 医療保険分 | |
|---|---|
| 所得割(前年の総所得金額から基礎控除を引いた額に割合を乗じる) | 5.0% |
| 均等割(被保険者1人につき) | 19,800円 |
| 平等割(1世帯につき) | 15,000円 |
| 賦課限度額 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | |
| 所得割(前年の総所得金額から基礎控除を引いた額に割合を乗じる) | 2.6% |
| 均等割(被保険者1人につき) | 10,500円 |
| 平等割(1世帯につき) | 7,500円 |
| 賦課限度額 | 260,000円 |
|
介護納付金分 |
|
| 所得割(前年の総所得金額から基礎控除を引いた額に割合を乗じる) | 1.8% |
| 均等割(被保険者1人につき) | 9,300円 |
| 平等割(1世帯につき) | 4,500円 |
| 賦課限度額 | 170,000円 |
国保税の軽減・減免措置について
◆所得が少ない世帯の軽減について
前年の世帯の所得(世帯主+被保険者(※1))が一定基準以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。世帯に町県民税未申告の方がいると、軽減が適用されませんので、必ず申告をしてください。
税制改正に伴い、令和7年度からの軽減基準が変更となります。
| 令和6年度 | 令和7年度 | 軽減割合 |
|---|---|---|
| 43万円+{(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円}以下 | 43万円+{(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円}以下 | 7割 |
| 43万円+(29.5万円×被保険者数)+{(給与所得者等の数-1)×10万円}以下 | 43万円+(30.5万円×被保険者数)+{(給与所得者等の数-1)×10万円}以下 | 5割 |
| 43万円+(54.5万円×被保険者数)+{(給与所得者等の数-1)×10万円}以下 | 43万円+(56万円×被保険者数)+{(給与所得者等の 数-1)×10万円}以下 | 2割 |
(※1)・・・被保険者等には、特定同一世帯所属者(国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に属する方)を含みます。
(※2)・・・給与所得者等とは、給与収入55万円を超える方、または、公的年金等の支給(公的年金等の収入額が、65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を受ける方(給与所得を有する者を除く。)をいいます。
◆未就学児の均等割額5割軽減について
義務教育に就学する前のお子様がいらっしゃる世帯については、そのお子様分の均等割額が5割に軽減されています。上述の所得が少ない世帯の軽減措置を受けている世帯は、軽減後の額がさらに半分になります。
(例)7割軽減を受けている世帯は、均等割額(医療保険分)が5,940円(19,800円の3割)ですが、未就学児のお子様の分は、そこからさらに半額の2,970円になります。(後期高齢者支援金分も同様に軽減されます。)
◆産前産後期間に係る所得割額・均等割額の一部免除について
出産した被保険者の方の所得割額と均等割額について、産前産後の4か月相当分を減額します。免除を受けるには手続きが必要です。対象の方には別途ご連絡いたします。
◆後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減について
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に加入し、75歳未満の方が引き続き国保被保険者のまま1人のみの世帯(特定世帯)となる場合には、5年間、平等割額の2分の1が減額されます。その後も世帯構成が変わらない場合(特定継続世帯)、さらに3年間、4分1が減額されます。
◆旧被扶養者に係る減免について
75歳になる方が会社の健康保険などの被用者保険を抜けて後期高齢者医療制度に加入することにより、その扶養家族である扶養家族であった被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、当分の間、所得割が賦課されず、均等割額並びに平等割額が2年間半額になります。(事業主が発行する資格喪失証明書に喪失理由の記載が必要です。)
なお、上記の所得が少ない世帯に対する7割、5割の軽減に該当する場合は本減免の対象となりません。
国保の加入・脱退の手続きは14日以内にお願いします
職場で社会保険等に加入しても、役場窓口で国保の脱退手続きをしないと、国保税と社会保険等の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
逆に国保加入の手続きが遅れると保険証も交付されませんし、資格を取得した月までさかのぼって国保税を納めなければならなくなります。